故郷の味を求めて-臼杵市へ

旅の目的は、姉母の五年祭であったので、祭が終われば帰路につくこととなるが、同じ道を引き返すのは芸がない。そこで、四国に渡り高松経由で帰る計画を立てた。山陰の鳥取から九州へ、さらに四国へと巡るこの旅は、西日本を一周するようなかたちとなった。
なぜ、このような旅程を組むのかと問われれば、「明日は分からない」と思うからである。すでに膝を痛め、思うように歩けなくなった私だが、体力が残っているのは幸いであった。
四国への玄関口として選んだのは、臼杵港から八幡浜港へ向かうフェリーである。三年祭の際には別府港から乗船したため、今回は別のルートを選んだ。出航前に臼杵の町を観光するつもりであったが、あいにくこの日だけは雨に見舞われた。
臼杵には有名な臼杵石仏があるが、二年前に近所の方を案内して訪れたため、今回は割愛し、市内の味噌や醤油の醸造元を訪ねることにした。
NHKの「探検ファクトリー」にて紹介された、臼杵のフンドーキン醤油工場を訪れた。ここは、日本一の大きさを誇る木樽を有し、伝統的な醸造技術と現代的な生産体制とが共存する、まさに“生きた食文化の現場”である。
フンドーキン醤油は、創業明治6年(1873年)。元々は味噌の製造を本業としていたが、やがて時代の流れと共に、醤油やその他の調味料へと展開を広げていった。臼杵という港町の地の利もあり、九州各地から良質な原材料が集まり、また海外との交易を通じて技術と知恵が交流された背景もある。この地で培われた醸造文化が、フンドーキンという一つの屋号に凝縮されているのである。
九州の醤油は、一般に“甘口”で知られる。その味の背景には、温暖な気候の中での保存性の工夫や、砂糖文化の影響があるとされる。中には通常の醤油の五倍もの甘さをもつ商品も存在するが、家庭で使いやすいのは三倍ほどの甘さを持つものという。単なる甘さではなく、柔らかな旨味と深みを感じる醤油である。
訪れたのは、連休の谷間であった為、あいにく工場の案内人は不在で、木樽に間近で触れることは叶わなかった
フンドーキンの味噌工場と店舗は港の近くにある。

次に訪れたのは、こぢんまりとした味噌・醤油の工場「カニ醤油」である。以前にこの工場の味噌をいただいたときの美味しさが忘れられず、訪問した次第である。
臼杵市内には、フンドーキンの他に「富士甚醤油」という大きな工場もあるが、カニ醤油はそれらと比べると規模は小さい。しかし、ホームページを拝見すると、その工夫と発信のユニークさは抜きんでており、訪問前から興味が募った。


店内には思わず笑ってしまうようなポップが数多く掲げられており、それらを読みながらつい笑い声を漏らしてしまった。そして、気づけば手にした籠は味噌と醤油でいっぱいになっていた。

私は旅に出ると、ついその土地の味噌や醤油を買い求めてしまう。持ち帰りに苦労するのは毎度のことである。しかし、幼い頃に口にしていた味噌や醤油は臼杵のものであった。もう一度、あの懐かしい故郷の味に触れたくて、買い込んでしまうのも致し方ないことである。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。











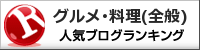

この記事へのコメントはありません。