風と土の工藝1n琵琶湖高島2013

風と土の工藝は今年で4回目になる。
毎回心を惹きつけられるポスターが送られてくる。
メンバーに写真家がおられるようだ。
懐かしい田舎風景の写真は大勢の人を高島に向かわせている。
風は他所から移り住んだ人、土は高島で生まれた人、一緒になれば風土となる。
ということから風と土の工藝の名前になったように記憶している。
今回は50名が参加し前半後半の分かれての開催になった。
鍛金の藤田良裕さんは今年初めて参加された移住1年目の方。
早速工房を訪ねると、

天井の高い広い工房にコークスが燃えていた。
スペインのガウディに誘発されてドイツのマイスターについて鍛金を学んだという経歴の作家さん。
作品のほとんどはパネル展示になっていたけれど、デザイン性があり鉄の重量感を感じさせる作品だった。
可愛い奥様がhand Warmerの代わりにと熱いお茶のTea Cupを手渡してくれた。
何気ないおもてなしが嬉しかった。

帆布を使った袋物の制作。
ちょっとゴワッとした感じの厚手の帆布だった。
展示用の棚とパーテーションはSoup Funitureの雄倉さんが作られたそうだ。
「かんじる比良」と「風と土の工藝」のジョイントかな。

ポシャギの作家さん若山佳代子さんとガラス工藝の久男さんの家
ストーブの煙突から流れる煙が紅葉した裏山に登っていく美しい風景に見とれた。
最近とみにポシャギに惹かれる。
繊細な針運びの芸術だ。
高島では若い人が古民家を再生して住み始めている。
アクセサリー作家のワダマキさんもそんな一人。

獣害よけのゲートをくぐって行く山の中

この家はワダマキさんが一目ぼれして今年の7月から再生に取り組んでいる。
ご主人は林業の傍らワダマキの情熱に引っ張られて再生を手伝っているのだとか。
イベントに合わせて大きな薪ストーブがどーんと置かれていた。
山の中だから薪には困らないと、土間の床暖房も薪で作ったそうだ。

前川 俊一さんの陶芸
写真で見ても現物を目の当たりにしても陶器とは思えず、金属だろうと思ってしまう。
それは一度焼いたモノの上にプラチナを塗り低い温度で再度焼いているからと説明された。
作品の展示も工房の作りも面白く、家の中を探訪させてもらった。

普段は洗濯物干しという小さなコーナーは奥様のレギーナさんの作品を展示
3方がガラスで明るく心地よい空間だった。
前川さんはスウエーデンやヨーロッパで陶芸を学び、奥様のレギーナさんは日本に陶芸を学びにこられたスイスの方だそうだ。
作品は茶道具はレギーナさんで前川さんの作品はヨーロッパの香りがする。
朝ごはんの後はそれぞれの工房にこもり、昼ごはんはどちらかが作り、夕方5時過ぎからは近くのプールに泳ぎに行くのが日常だそうで、心豊かな生活を送られている。
風と土の工藝は12月6日(金)から後半が始まる。
後半は農業や漁業、造船、古民家再生という分野の方が多いようだ。
見ごたえがあります、ぜひどうぞ。
skog企画展「しまいの月の贈り物」は12月13日(金)より17日(火)までの5日間
![1312_dm[1].jpg](http://img-cdn.jg.jugem.jp/934/1463255/20131130_518226.jpg)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。








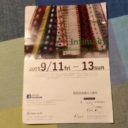





前川さん、レギーナさんご夫妻の写真の中に赤い屋根の家が写っていますが、私の生家なんですよ!
今は、亡くなった父の弟夫妻が住んでいます。
小5の二学期までそこに住んでいた、懐かしい故郷です。
ayayaさん、そうでしたか。
いい感じで写りこんでいますねえ。
緑が多く、川も流れて芸術家の巣のようなところでした。