「水神」帚木蓬生ー筑後川の流れの下に

博多で暮らしていた頃、私はよく筑後川沿いに車を走らせた。
筑後川は九州一の大河。流れに沿って温泉町が点々と並び、周囲にはゆったりとした田園風景が広がる。
小説の舞台にもなった吉井町は、白壁や鏝絵で知られ、今も往時の面影を残す町である。
なかでも「うきは」といえば果物の産地。いちごに始まり、ブルーベリー、梨、そして富有柿へと、季節ごとに実りが続く。私はこの町で、すっかり“フルーツ漬け”になった。
しかし、この豊かさは決して自然に与えられたものではなかった。
寛文4年(1664年)1月。江戸幕府の治世下、筑後川流域では深刻な水不足が続いていた。台地に住む農民たちには大河の水は届かず、田は干上がり、年貢の負担は重くのしかかる。飢えと隣り合わせの暮らしである。
その状況を変えようと立ち上がったのが、地域の五人の庄屋であった。
大河を堰き止め、水を引き、渇水に苦しむ村々へ分配する。今でこそ土木技術は発達しているが、17世紀当時、それは命懸けの大工事である。しかも下流域の庄屋の半数は反対に回った。水利をめぐる争いは、村の存亡に直結する問題だったからだ。
役人を動かすためには、身代も家名も、そして命さえも差し出す覚悟が必要だった。
帚木蓬生著『水神』(上下)は、その五人の庄屋と、名もなき農民たちが灌漑用水路を築く闘いを描いた物語である。
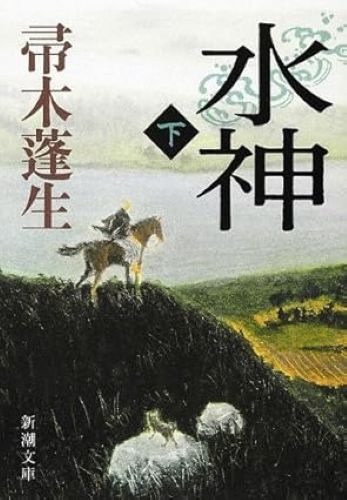
延宝2年(1674年)、幾多の困難を乗り越え、大石堰はついに完成する。
その後整備された大石長野水道は、農民たちの長年の努力によって維持され、現在もなお下流域約30平方キロに及ぶと言われる水田地帯を潤しているという。
悠々と流れる筑後川。
その静かな水面の下に、これほどの犠牲と覚悟の歴史が刻まれているとは、私はこの本を読むまで知らなかった。
今、私が何気なく味わっている果物の甘さ。その背後には、三百年以上前に命を懸けた人々の決断がある。
そう思うと、あの川をもう一度見たくなった。
記念碑もあるという。
今度はただ景色を眺めるのではなく、水の重み、歴史の重みを感じながら立ってみたい。
次に筑後川を訪れるとき、私はもう以前と同じ気持ちでは立てないだろう。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。












この記事へのコメントはありません。